 |
| HOME| Coffee Break| Profile| FDG Part-1| ENGLISH| FDG Part-2A| FDG Part-2B| Other Stories| It's a small world !| アット・ホームページ| @nifty |
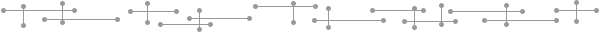 |
 FDG Part-2
FDG Part-2 |
 |
|||||||||
 Fragments
Fragments
|
<Scene> 長いランニングを終えたとき、Folk教授はその理論を完成させていた。 「..........」 声にならない何かをつぶやき、彼はそのまま地面に倒れこんだ。 </Scene> <Scene> 12月のマウイ島は奇妙な光景だ。3メートルはあるでかいクリスマスツリーの横を水着のカップルが通り過ぎる。 「じゃあね。Have a nice Christmas!」 すっかり気分のよくなったDr.Bambooはアロハシャツの運転手に4ドルのチップを手渡した。 「You,too.」 自分の将来を祝福するかのような返答にDr.Bambooは酔いしれていた。 :::::::::::: 「ち、これっぽっちでクリスマスが過ごせるかよ。ま、昼飯の足しにはなるけどな。」 センターから次の客の居場所が無線で告げられた。 </Scene> <Scene> 「歴史的必然? そんなものは簡単に書き換えられるさ。 今じゃ、個人の歴史的事実さえも風評で操作できる。Presentationされないデータは無効なんだよ。」 Highがはき捨てるように言った。Hotはうなづいた。 </Scene> <Scene> MickyはMITの構内ですっかり迷ってしまった。仲間たちはもう、ホテルに帰っただろうか。あたりは夕闇が迫っている。 そのとき、噴水のむこうからまばゆいばかりの光を放つ女性が近づいてきた。 「どうかなさいましたか?」 「あ、あのー、道にまよってしまったんですけど。」 「学会に参加されてる方?」 「はい、Micky Tree、日本人です。」 彼女は颯爽と歩き、大通りに面した正門まで案内してくれた。 「ありがとうございました。よろしかったらお名前を。」 「私? 私の名前はRena。Rena D. Folk。情報科学の理学博士よ。」 </Scene> <Shot> 「数式を書いて自分の死を自ら証明した人もいる。 僕が生きながらえたのはわずかに最後の不等式が反転しただけかもしれない。 もちろん、そんな証明、実際に紙の上でしたことはないけどね。」 </Shot> |
 |
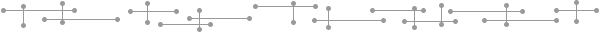 |
 And Particles
And Particles |
<Shot> Heavy Metal社の一室。 「ああ、Folkはもう邪魔だ。何とかしろ。ただし、タイミングを間違えるな。いいな。」 Redは受話器を置いた。 </Shot> <Scene> 「おー、なかなかいいねー。だいぶ“かんせい”に近づいてきたねー。」 「所長、それ、洒落ですか?」 「うるせー、よけいなこといってねーでさっさと楽しい開発しろ、このやろー。」 「はーい。でも、やっぱ、あとは“ハート”の部分ですよね。」 「マシンの“ココロ”か。そういえば、昔、そんなことやってる偉い学者もいたなー。」 Dr..Bambooは10年前に浜松の世界的楽器メーカーをスピンアウトし、今は有限会社Music Scene Researchの代表取締役兼所長である。とはいえ、社員は彼を含めてまだ5名。ほとんど特許収入と芸能界向けのソフトウェア開発で何とか持ちこたえているベンチャー企業である。しかし、最近、ようやく彼の永年の夢であった音楽映像自動生成マシンのプロトタイプが完成し、徐々に業界の注目を集めるようになっていた。 「では、君たち、今日は大事なパーティがあるのでお先に。」 「あ、営業、ご苦労さんです。」 Dr. Bambooは愛車のスポーツワゴンで会場に向かう。仕事とはいえ、別にパーティーなんか出たいわけではない。ただ、星空と子供の寝顔しか眺めていない最近の彼は疲れていた。そんな彼にとって、公然とハイウェイから夕日を眺められる時間は、予測される煩わしさをしばし意識から消し去るのに十分な効果があった。 </Scene> |
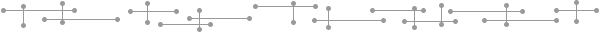 |
 To be organized
To be organized |
<Shot> - ボストン郊外のレストラン。 「今日ねー、日本人が大学構内で道に迷ってたので正面玄関までお連れしたわ。」 「ほー、何しにきたんだ?」 「学会よ、情報通信関連の。」 「その人、日本語のガイドブックとか持ってたんだけどー。私、日本語はよくわからなくて。」 「6ヶ国語自在の君でも日本語は難しいのかい?」 「だいたい、あの”漢字”とか”ひらがな”とか”カ タカナ”とか、どうして幾種類もの文字が混在した 文書が読めるのよ、信じられない。韓国語なら少し 知ってるけど、ハングル文字1種類で書けるわ。」 「何だ、結構知ってるじゃないか。」 「まーね。でもギリシャ語やラテン語のほうがまだましよ。まったくどういう認識処理してるのかしら、日本人て。おまけに”大阪弁”とかあるらしいし。」 「君なら1年も住めば自由自在さ。言語って結局、経験と学習能力なのさ。xx語っていうのは人が勝手に決めた分類ラベルだろ?」 「そーね。」 Renaはワインをぐっと飲み干した。 |
 |
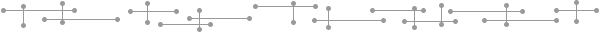 |
 Party
Party
|
<Shot> 東京・品川のとあるパーティー会場―――。 「やあ、Bamboo君、久しぶりだね。調子はどうだい?」 「いやー、まずまずです。」 「君がこの間、業界紙で発表した、あの、何とかというマシンね、あれは一体何だね?」 「あー、あれは音楽の曲想を解析し、そのフィーリングにあったイメージを自動生成するマルチメディアシステムでして、コンサートや広告に応用しようと考えています。」 「相変わらず、君の言うことはさっぱりわからんねー。ひとことでいうと何だね。もっとわかりやすく説明したまえ。」 「ひとこと?ですか? えー、ですからー、。。。。。」 「そーいうことだから、うちにいたときも出世できなかったんだよ。今はまがりなりにも社長だろう? 気をつけないとビジネスチャンスを失うよ。」 「はっ、ご忠告ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。失礼しまーす。」 Bambooは逃げるように料理を取りにいった。 「よー、Bamboo、随分、Hioki事業部長にいじめられたようだね。」 某放送局のKamiyaディレクターが片手にグラスを持ったままでBambooの肩をたたいた。 「いやー、業界のドンには逆らえないよ。クワバラ、クワバラ。」 「まー、気にすんなよ。例のマシンさ、俺のところで使ってやるから。もう番組の企画もほぼ決まってるんだ。来週、一度見に行くよ。そのとき詳しく打ち合わせよう。」 「あっりがとうございまーす!Kamiyaさんは“神様”でーす。」 「ばっか。ふざけてんじゃねーよ。じゃー、社員と嫁さんによろしくな。」 Bambooは思いきり頭を下げてお辞儀をした。今夜の営業はまずまずの成果だったようだ。 </Shot> |
 |
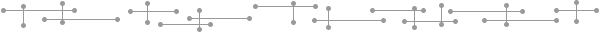 |
 Expected Timely Harvest
Expected Timely Harvest |
<Shot> 少し霞んではいるが、湖の遥か向こうには今も氷河を見おろす“Top Of Europe”があるはずだ。湖岸を確認して静かに視線を右に移動すると、空に向かって針のような3つの教会が等間隔でそびえたつ――。そんな市内を一望できるこの遊歩道にも秋が訪れようとしていた。 「おはようございます、Folk教授。」 「ああ、学長、こちらこそおはようございます。めずらしいですね、いつもご多忙な身なのに。」 「これでも学者魂は健在です。時間があるときはいつも物理学教室をのぞいていますよ。」 連邦工科大学学長、Dr.Forschungは穏やかな顔で答えた。ForschungはFolkの2年後輩だったが、その奥ゆかしい人柄のためか、Folkは何の抵抗感も無く日々の大学生活をすごしていた。 「学長もかつては大統一理論(GUT)に身を捧げていたのでしたね。最近は超弦理論がにわかに脚光を浴びているようですが、どんな状況です?」 「ああ、スーパーストリングですか。それにしても“かつては”とはひどいなあ。まだ現役ですよ。」 二人は顔を見合わせながら高らかに笑った。 「それにしてもよかった。Folkさん、すっかり元気になられて。」 「これもすべてあなたのお誘いがあったからこそ。感謝しています。」 「感謝なんて、そんな。世界的頭脳が埋もれていくのを研究者として見過ごすわけにはいかなかっただけですよ。」 「あー、あの頃は確かに大変でした。上の娘はいまだにあちらでがんばっていますけどね。」 「そうでしたね。Folkさん、ご実家はBernでしたっけ。故Einstein博士も住んでおられたという。」 「ええ、週末はいつもAare川のほとりをジョギングしていますよ。」 「ああ、対岸に市庁舎がある大きな橋のたもとあたりですね。私も大好きですよ、あの辺は。最後の石段が結構きついですけど。」 「はっはっは。よくご存知で。」 「話は変わりますが、Folk教授、近くあのProfit財団が本学を訪問したいと言ってきています。Profitと関係の深いHeavymetal社というのも同行するらしく、何でもあなたのご研究に大変関心があるとか。」 「あのProfitが?」 「正式に決まったらご連絡いたします。では、また。奥様やお子様たちにもよろしくお伝えください。」 にわかに多忙さを取り戻したForschungはそう言い残して学内に消えていった。 </Shot> |
 |
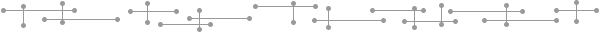 |
 Cocktail
Cocktail |
<Shot> パーティーはまだ続いていた。ん?、何やら遠くで聞き覚えのある声が。認知心理学ではカクテルパーティ効果と呼ばれている。 「フェルメールっていう作家の特集番組、随分話題だったようだね。」 「作家じゃなくて、画家ですよ。17世紀のオランダの。」 「ふーん。どこが受けたポイントだったのかなあ。ひとことで説明してくれる?」 「ひ、ひとことですか? そ、そーですねー、。。。」 :::::::::::::::::::::::::::: 「あ、Kamiya君ひさしぶり。このあいだの大河ドラマよかったそうだねー、人気の秘密を30秒で説明してくれない? 要点を簡潔にね。」 :::::::::::::::::::::::::::: ご愁傷さま。 </Shot>
<Shot> 噴水がとまり、やがて、あたりにちらほらと街灯が点き始めた。 「おい、あの“じっちゃん”また、来たぜ。」 スケボーの少年たちが囁いている。 「あーあのおっちゃん? 俺が小学生のころから毎週ここを走ってるよ。“じっちゃん”はねーだろ。そーいえば最近、少しふけたかなー。」 「”じっちゃんになりかけて”ってか?」 「はっはっは! やるなーおまえ。」 Yuuyaが珍しく高らかに笑った。”じっちゃん”はとうに橋を渡りきり、健康センターの階段をのぼりかけている。Takeshiは話を続けた。 「なんかさー、いつも回りは眼中にないって感じなんだよなー」 「走り終わるといつもあの階段のてっぺんで夕陽をみてるだろ?」 「あー、そうそう。で、ときどき、『そうか』とかつぶやいてんだよね。」 「キモー。まーでも害はないからほっとけよ。」 「そーだな、大会近いし。」 「しっかし最近変な中高年が増えたよなー。」 あたりはいつもの夕闇に包まれつつあった。道路を隔てて町立テーマパークの中に建つ時計台がいい雰囲気をかもし出している。そして針はまっすぐになろうとしていた。その背後のはるか遠方にはオレンジ色の空が最後の輝きを放ち、やがて航空機が悠然と通り過ぎていく。 「うちの親父がいってたぜ。“ダンタイのせだい”とかいうのがいーよーに世の中変えちゃったんだって。」 「“ダンタイ”? ちょっと違うよーな気がするけど。まーそんなもんだろ。若いころ“いちご白書”だとかいう映画みて髪のばしてさー、反戦フォークだの革命だのというファッション気取ってた連中さ。」 「流行だったんだよなー、ただの。結局、アメリカとかから輸入されたものを真似てただけさ、別にあの世代が偉いわけでもなんでもねーよ。」 「おい、あまり騒がないほうがいいぜ、結構あの世代、社会に出てからは猫かぶってえらくなってる連中多いようだから。」 「そのくせ、影では組織の中で不良しまくってるんだぜ。」 「もーいーじゃないか。ほっとけよ。みんなじじいにばばあなんだからさー、あと10年もすればいなくなるよ。」 「よーし、もうワンラウンドいくか。あのコンクリートの縁をスライドしてこえられたら今日の課題は終了だ。俺からいくぜー。」 Yuuyaは勢いよく地面を蹴ってボードを発進させた。
</Shot> <Shot> ある朝、Shin-yaが目を覚ますと、見渡す限り荒野だった。 「俺のアパートはどうなったんだ?」 誰もいない。文明のかけらも感じられない。生き物さえ果たしているのかどうか。ただ、幸か不幸か気候は穏やかで、雲ひとつない秋の空といったところだった。 「ここはどこなんだ? 地球か? まさか、あの茂みから知能化した猿でも出てくるんじゃないだろうな? まーいずれにしても夢だろう、これは。じゃーいつものように羽ばたいてみよう。」 Shin-yaはいつも夢の中でやるように平泳ぎをはじめた。いつもはこれでかなり空を飛ぶことができる。しかし、今日はだめだった。どうも、物理的制約は正確に組み入れられた夢らしい。そうこうするうちに、夢の中とはいいながら、腹が減ってきた。何を食えばいいんだ? Shin-yaは魚を獲ることにした。でも釣竿は? 網は? 現世に戻れば1000円もあれば買える網もここでは作らねばならない。じゃあー槍にしよう。木を削ることにした。だが、ナイフがない。 「やばいなー、今日は新日本テレビ向けに大事なデモがあるんだけどなー。」 そんなことを気にしている場合か? 「まず、この夢から覚めなければ。 ん? 待てよ。」 そして彼はなぜか人殺しの罪で追いかけられていたことを思い出した。これもよくある夢のパターンだ。 「あー、俺の人生はもう終わりだ。でも誰をやっちまったんだ?」 日が翳ってきた。とたんに、また空腹感が押し寄せる。そして何の疑いも抱かずに彼は奇妙な論理を導出した。 「そうか、ここは俺の流刑地なのか。よし、俺はここに文明を築こう。」 何だか“火の鳥”の一節みたいな展開になってきた。 「まあ、俺のボヘミアンは今に始まったことじゃないさ。三歳にして銀ヤンマを追いかけながら、迷子になったからな。あのときは町中総出で夜まで捜索してくれたって親父が言ってたなあ。でも、あの銀ヤンマでかかったなー。よくあの破れ網で捕まえられたよなー。」 思っているのか喋っているのかわからないような独り言が続く。 そのとき、湖の対岸に人影らしきものが見えた。Shin-yaはまるで中国映画のワンシーンのように水面を裸足で三段跳びのように駆け抜け、その影を追った。 「何だ、やっぱり夢じゃん。こんなの現実じゃありえねーよな。」 しかし、ターゲットはまだ確認できなかった。 </Shot>
<Shot> 茂みを抜けると、岩場の絶壁のふもとに大きな洞窟があった。やつは確かにここに来たはずだ。Shin-yaは恐る恐る入ってみた。 突然、扉が現れた。迷わずあけると部屋があった。 そこには、床一面に蝋燭が並べられていた。炎はかすかな風のもとで、揺れ動いている。 「誰かな?」 男の声がした。 「ここは何の部屋ですか?あんた、新興宗教の教祖か何か?だいたい、何? このローソク。」 「これは“運命の蝋燭”じゃ。ほれ、これが君のだよ。」 何がなんだかわからない。いい加減な夢としか思えない。 「君の運命はもう決まっているのだよ」 「何だと、勝手に決めるな!」 そのとき、風が部屋の中を吹き抜けた。 「あ、おれの運命が!」 彼の炎は大きく揺らぎ、一瞬消えそうになった。 「死ぬのか、俺は?」 だが、やがてまた、炎はもとの大きさを取り戻した。 「はっはっは。パフォーマンスだ。来客はいつもこうやってもてなすことにしている。」 「ふざけんじゃねー。ったく、何考えてんだよ。」 「ただのホログラムだ。昔は本物の蝋燭が用いられていたんだがな、技術の進展とともに、三次元CGに置き換えた。ほら、葬式の蝋燭もいまや電飾だろう?」 そういえば、代替品がoriginalよりも幅を利かすことはよくある。蝋燭だって大昔はなかった。人類は泳ぐためにプールを作ったが、“泳ぐ”ということにかけてはいまや、海や川よりもあたりまえだ。 「どういうしかけなんだ、この運命の蝋燭は?」 「あれを見よ」 :::::::::::::: </Shot> <Shot> 「そうではない、ただ、光が外に漏れるとまずいことが起きる。」 「えー?、洞窟の中だろ、大体何で窓があるんだ? ま、どーせ夢なんだ、あけちゃえ。」 なんと外は先ほどの湖面につながっていた。あたりはすっかり闇である。 「ってことは、外は湖なのか。」 部屋の明かりがサーチライトのように湖面を照らした。 「おい、早く閉めろ。危ない。」 「えっ、何が危ないんだ?」 そのとき、水面から銀色の槍のようなものが飛び出し、Shin-yaの頭をめがけて近づいてきた。「うわー」間一髪よけた彼は、何がなんだかかわからない様子だった。 ターゲットをそれた銀色のやりは部屋の中に飛び込み、床で暴れ始めた。なんとそれは魚だった。みたところ、体長は秋刀魚二匹分というところだ。 「何だこりゃあ。あっぶねーな。でもこれで一食分にはなるか。」 だが、よく見るとあまり身はなさそうだった。 「お前よく命拾いしたな。これはオキザヨリといってな。」 「知ってる、ダツの仲間だろ。沖縄あたりで夜釣りしてるとライトめがけてつっこんでっくるという話を聞いたことがあるよ。腹とか頭に刺さって死んだ人もいるとか。」 なるほど魚の口はドライバーのように尖っていた。 「まさか、こんなとこにいるとはなー。大体部屋の窓を開けて飛び込んでくるなんて思いもしねーよ」 </Shot> <Shot> :::::::::::::::::::: 「あなたの名前は?」 「私か? 私は……..」 そのとき、地面が大きく揺れ始めた。壁の石が無造作に転がり落ちる。 Shin-yaはあわてて外に出た。そしてまた、水面を蹴って飛び始めた、ワン、ツー。 「あ?」 スリーステップ目に足が水面にめり込んだ。とたんに彼はただの人となり、水中に沈み始めた。 「あーーーー」 もがくが、沈んでいくばかりだ。全身が海水で濡れていくのを感じた。薄明かりの中で何か近づいてくる。 「あー、やばい、今度は鮫だ。絶体絶命!」 そのとき、水中でShin-yaの好きなストーンズの曲が鳴り始めた。 「今、それどころじゃねーだろ、ミスマッチな夢だな。あっ、そーか!!」 それは彼のジーンズのポケットに入れたケータイだった。 “ …. can get no satisfac……..” 目が覚めると、あわただしい点滅とともに携帯が曲の続きをやっていた。 「お、まさか」 子供のころの記憶が一瞬よみがえったが、大丈夫だった。Shin-yaは携帯を手に取った。 「あ、もしもし」 「俺だ、Bambooだ。どこにいるんだお前?」 「Bamboo? 誰それ?」 「ざけんじゃねー 何ねぼけてんだこのやろー」 「あ、社長、ていうことは、あああもうこんな時間か」 「お前、今日は10時から首都東京TV向けのデモがあるから、8時半までにはリハーサルを開始するように準備しろっていっただろ。9時になってもこねーじゃねーか。社運がかかってんだぞ、社運が。」 「す、すみません。大急ぎで行きまーす。」 さいわいにMSR社は自転車で15分ほどの池のほとりにあった。 Shin-yaは髪もぼさぼさで自転車に飛び乗った。全速力で走らせる。 こんな日は一度でも立ち止まると消えてしまいそうな気がした。幸いに信号には一度もひっかからなかった。 「着いた、9時22分。自己ベスト更新か? 」 ほっとしたShin-yaは何か右頬に痛みを感じた。 「いてー、何か、寝てる間にぶつけたか? 」ミラーで覗くと赤い切り傷ができていた。手で触ったとき、一枚の光る薄片が落ちた。だが、Shin-yaはそれに気づくひまもなくオフィスに駆け込んだ。 </Shot> |
|||
 |
 |
 リンク集 リンク集 |
 アット・ホームページ アット・ホームページ |
ホームページ開設サービスです。 |
 @nifty @nifty |
@niftyのトップページです。 |
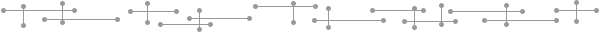 |
| HOME|Coffee Break|Profile| FDG Part-1| FDG Part-2A| Other Stories|It's a small world !|アット・ホームページ|@nifty |
|

